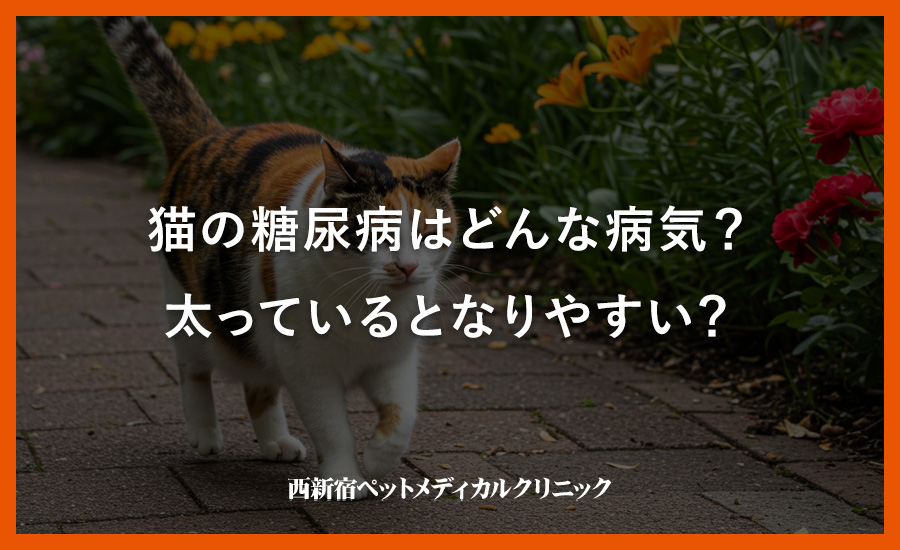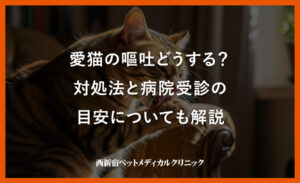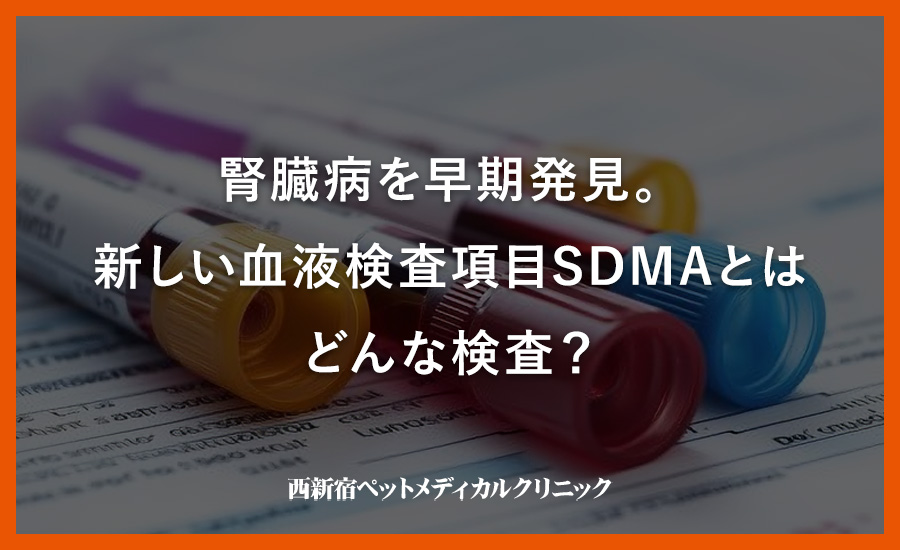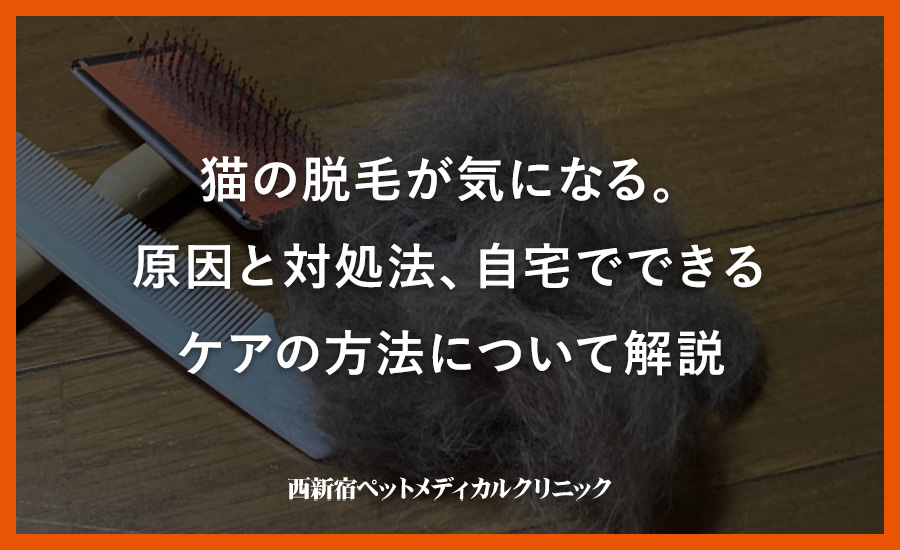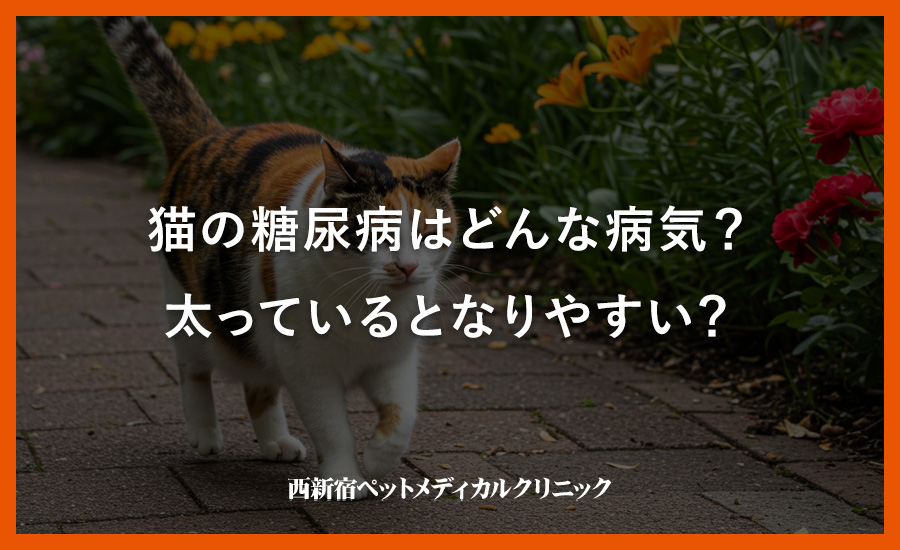
愛猫を守るために知っておこう〜猫の糖尿病について〜
愛猫家の皆さん。
猫の糖尿病についてご存知でしょうか?
愛猫を守るために、猫の病気について知識を深めておくことは大変重要です。
ここでは、愛猫を守るためにぜひ知っておいて欲しい。
猫の糖尿病について詳しく解説いたします。
猫の糖尿病ってどんな病気?
猫の糖尿病は、血中の糖が増える病気です。
インスリンが足りない、もしくは正常に働かないことによって引き起こされます。
通常、血液中の糖はインスリンにより細胞内に取り込まれます。
そしてこれが、各臓器を動かすエネルギーとなっています。
しかし、インスリンの働きが悪く、糖を細胞内に取り込めないとなると、血液中の糖が増え飽和状態になってしまいます。
一方で、細胞内の糖は足りなくなります。
猫の糖尿病においては、食事療法を行うことで、体内のインスリンが正常に機能することが多くあります。
人間の糖尿病に例えると、2型糖尿病に似ていると言えます。
ここで参考までに、私たち人間の糖尿病についてみてみましょう。
人間の糖尿病
人間の糖尿病には、2種類あります。
「1型糖尿病」と「2型糖尿病」です。
1型糖尿病は、膵臓がインスリンを作れなくなってしまうことにより糖尿病を発症します。
治療法は、インスリン注射です。
2型糖尿病は、生活習慣や遺伝が原因で、膵臓からインスリンが出にくくなる、もしくは、出てはいるが働きが悪いことにより発症する糖尿病です。
2型の場合は、食事療法、運動療法、血糖値を下げる薬、場合によってはインスリン注射による治療が行われます。
猫の糖尿病の症状は?
猫の糖尿病の症状を見てみましょう。
猫の糖尿病には、次のような症状を伴います。
- 水を飲む量が増える
- 尿の量が増える
- 毛ヅヤが悪くなる
- 食欲はあるが、痩せてくる
上記のように猫が糖尿病になると、水を飲む量が増えて尿の量が増える多飲多尿の症状がみられるようになります。
尿に糖が混じっていると、尿の量がいつもより多くなります。
また糖と一緒に水分も大量に放出されます。
これにより体内の水分量は激減するため、それを補うため多飲になるのです。
また糖尿病の場合、糖が体内に吸収されにくくなるので、食欲はあるのに痩せていくという現象がみられます。
猫の糖尿病の原因とは?

猫の糖尿病の原因は、おもに3つ挙げられます。
不適切な食事
猫は肉食動物です。
そのため、動物性のタンパク質を摂取しなくてはなりません。
一方で、炭水化物はあまり摂取する必要はありません。
にもかかわらず、低タンパク質、高炭水化物といった不適切な食事を続けていると糖尿病にかかるリスクが高まります。
肥満
肥満も糖尿病を引き起こす要因のひとつです。
体重が増え肥満になると、糖分を細胞に取り込む役割をしているインスリンの働きが悪くなります。
これにより糖尿病発症のリスクが高まるのです。
膵炎
膵炎とは、糖分を細胞に取り組む役割をしているインスリンが作られるのは膵臓です。
この膵臓に炎症がおこる病気が、膵炎です。
膵炎になると、膵臓が破壊されインスリンが製造されなくなります。
また激しい炎症によりインスリンの働きが悪くなります。
これらが引き金となり、糖尿病を発症するのです。
このほか、ウイルス感染やクッシング症候群なども糖尿病の要因になる場合があります。
糖尿病にかかりやすい猫はどんな猫?
糖尿病にかかりやすい品種はありません。
全ての猫種がかかる可能性がありますが、強いて言えば、肥満体型の猫は糖尿病になりやすいと言えます。
猫の糖尿病の治療法について
猫の糖尿病に治療には、大きく2つの方法があります。
それぞれについて見ていきましょう。
食事療法
猫の糖尿病のおもな治療法としては食事療法があります。
血糖値をコントロールしやすいように、糖尿病用の療法食に変更します。
注意すべきポイントは、療法食以外のフードを食べさせないことです。
愛猫の手に届くところに食べ物を置いておかないこともポイントです。
インスリン注射
インスリン注射は、血糖値を安定させるために投与する糖尿病の主な治療法です。
インスリン注射は、基本的に毎日1日2回打ちます。
飼い主さんが、自宅で愛猫に打つようになります。
飼い主さんのライフスタイルによって、インスリン注射をする時間なども異なることから、目標とする血糖値も異なってきます。
インスリンの注射の量や血糖値測定のための受診頻度など、かかりつけの動物病院の医師とよく相談しましょう。
また、糖尿病性ケトアシドーシスを起こしている場合には、救急管理が必要になります。
糖尿病性ケトアシドーシスとは、糖尿病を発症している際に起こる緊急を要する病状のことです。
食欲が低下し、元気もなくなり、脱水症状がみられるようになります。
糖を得られない細胞が糖の代わりに脂肪を分解するとき、ケトン体が多く製造されることが原因となる病状で、早急に適切な治療を行わないと死に至ることもあります。
糖尿病性ケトアシドーシスを発症している場合は、入院してインスリン注射を投与しながら、静脈点滴を行ない、高血糖、脱水、電解質バランスを整える治療を行ないます。
まとめ
猫の糖尿病についてご紹介いたしました。
愛猫を糖尿病から守るためのポイントは、肥満を防ぐことと、ストレスのない環境を整えることです。
食事の管理を行ない、運動ができる環境を整えてあげましょう。
また快適に過ごせる空間を作り、ストレスのない生活を送らせてあげることも大切です。
この記事の監修者
獣医師 宮尾 岳
西新宿ペットメディカルクリニック 院長
新宿区の西新宿ペットメディカルです。
動物が病気になったときに治療することだけが獣医療ではありません。
日々の予防を喚起するのも自分の務めです。
日常の些細な疑問やケアからでも病院へ相談、もしくは足を運んで頂ければ幸いです。