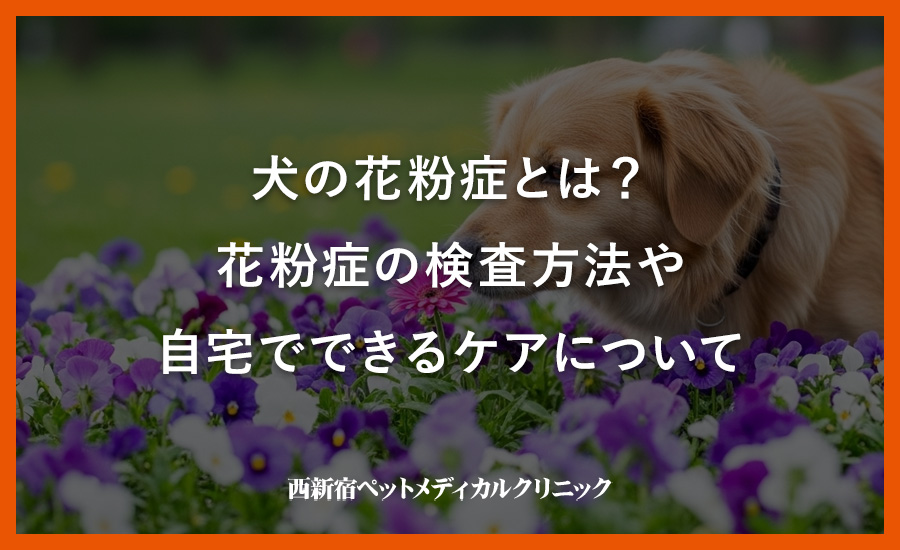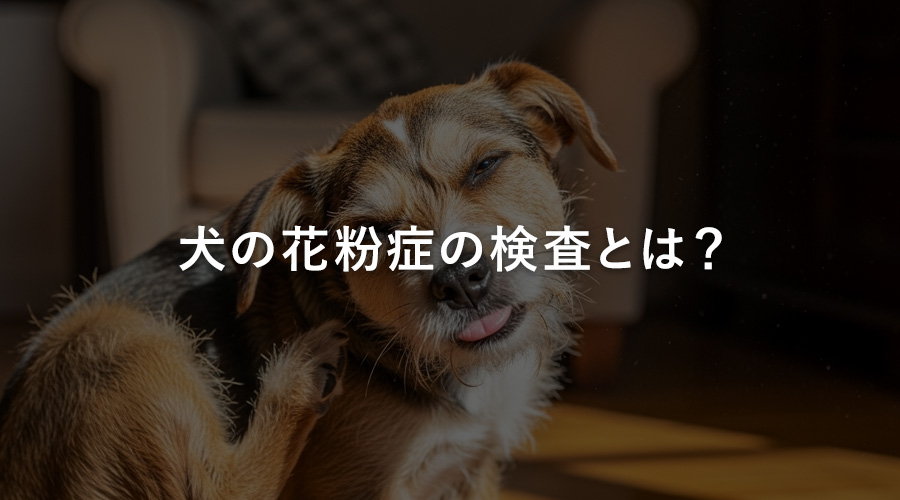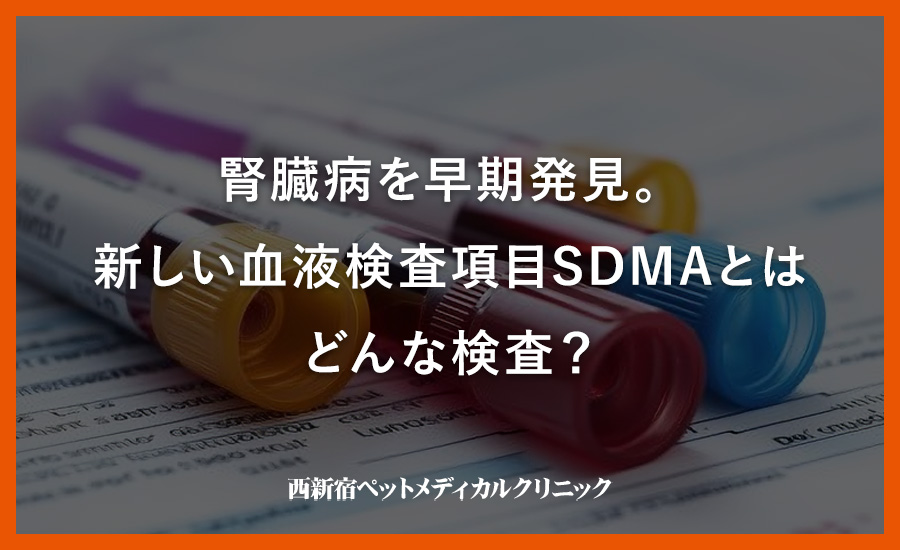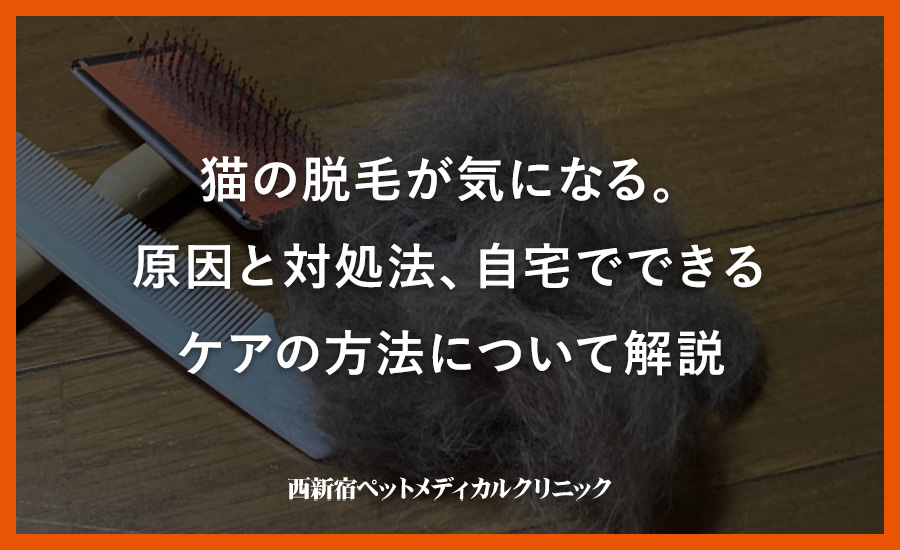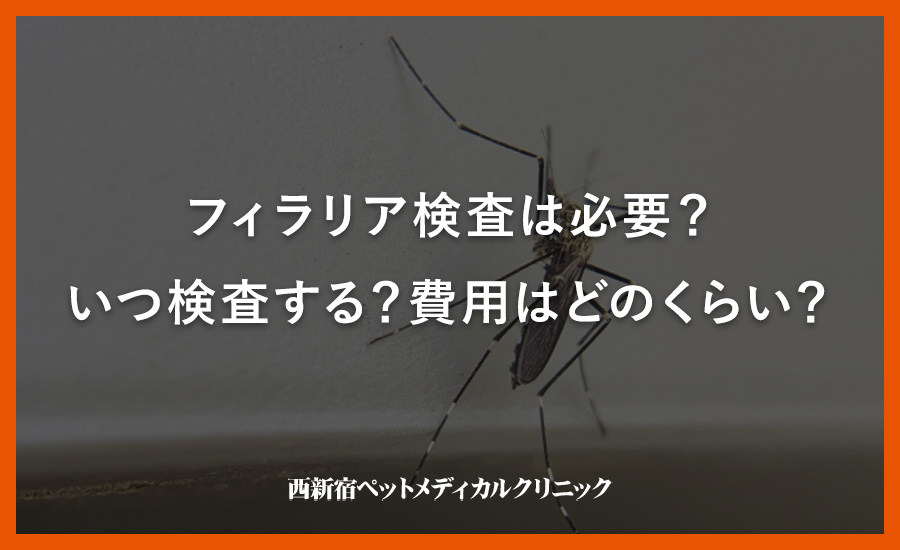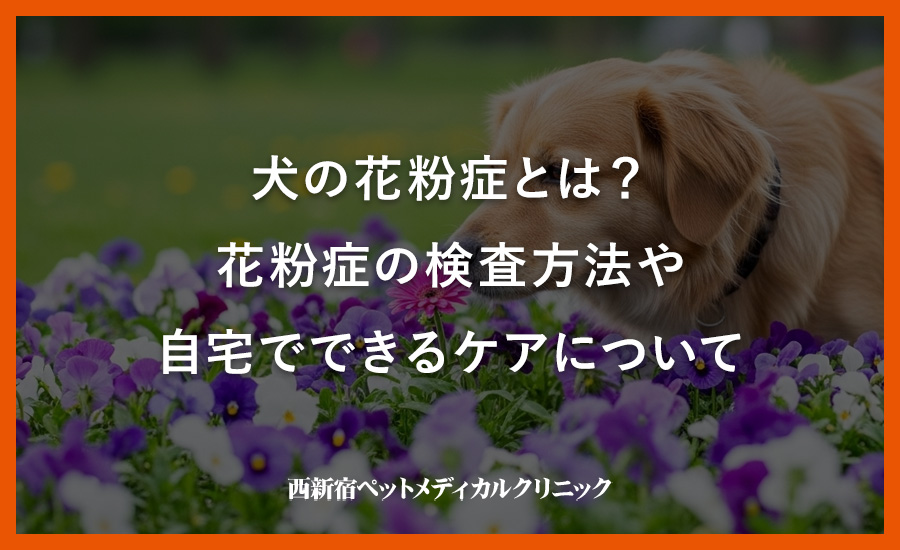
私たち人間も花粉症の方は、春や秋、花粉症に悩まされている方多いですよね。
実は、犬も花粉症になることをご存知でしょうか?
ここでは、犬の花粉症の症状や治療、自宅でできるケアの方法についてご紹介いたします。
犬の花粉症とは?
花粉症とは、植物の花粉がアレルゲン(抗原)となり、体の免疫システムが過剰に反応することで発症するアレルギー疾患です。
スギやブタクサ、イネなど、さまざまな植物がアレルギーの原因となります。
人間は花粉症になれば、鼻水やくしゃみ、目の痒みなどが症状として出ますが、犬には人間のような症状はほとんど見られません。
犬の花粉症の症状とは?
犬が花粉症になれば、人間のような症状は見られませんが、皮膚や耳、消化器や呼吸器などに症状が現れます。
おもな症状は3つあります。
それでは、実際にどのような症状が出るのか見ていきましょう。
皮膚や耳の症状
犬の花粉症の症状でもっとも多いとされるのが、皮膚の痒み、発疹、外耳炎です
特に、目のまわりや口、耳、脇や股の下、足先に症状が出やすくなります。
痒いので、頻繁に掻いたり舐めたりするようになります。
また外耳炎になると、耳垢が増えるとともに悪臭がします。
痒みが強いので、かなり頻繁に掻いたりするようになります。
花粉症によるこれらの皮膚症状は、アトピー性皮膚炎と呼ばれることもあります。
下痢・嘔吐などの消化器症状
花粉が体内に入ると、腸内の免疫バランスが崩れます。
これにより下痢や嘔吐が起こることがあります。
花粉の飛散量が多い時期(春や秋)に消化不良を起こすことが多い場合、花粉症の可能性があります。
下痢や嘔吐などが続き重症化すると、便に血が混じったり、慢性的な下痢により脱水症状を引き起こすこともあるので注意が必要です。
鼻水や咳などの呼吸器症状
犬の花粉症の症状としては、呼吸器の症状はそれほど多くはありませんが、なかには、咳が出たり、鼻水や喘息の症状が見られる犬もいます。
特に、フレンチ・ブルドッグやパグといった短頭種は、気道が狭いため、軽い炎症であっても呼吸がしづらくなります。
呼吸がいつもより荒い、ゼーゼーと息をしている、咳が止まらないなどの症状が見られる場合には、早めの受診をおすすめします。
犬の花粉症の検査とは?
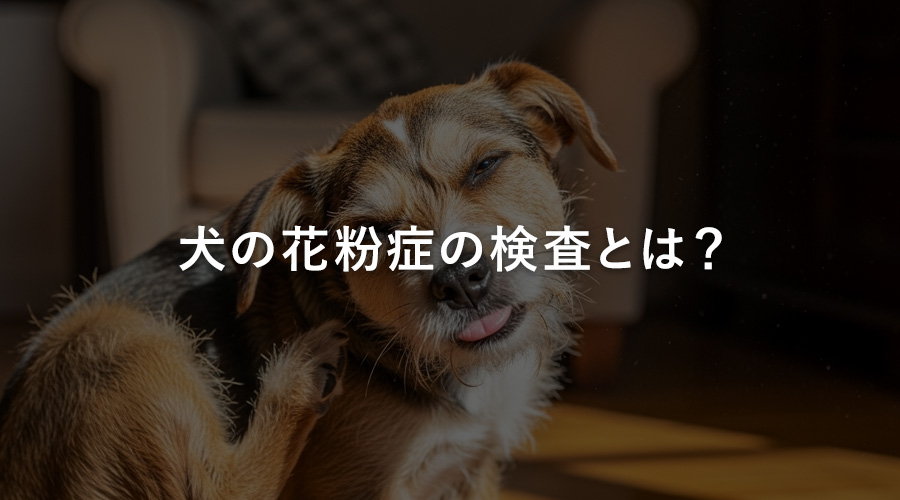
「うちの子、花粉症かも?」と思ったら、動物病院を受診しましょう。
花粉症などのアレルギー検査は、次の5つの検査を組み合わせて診断します。
皮膚科検査
皮疹や脱毛など皮膚の症状が出ている場合、皮膚科検査を行ないます。
皮膚掻爬検査(ひふそうはけんさ)やテープ検査、スタンプ検査などでは顕微鏡で皮膚の観察を行ない、感染症皮膚炎や寄生虫感染などについて確認を行ないます。
またより正確に診断するため、皮膚の一部を採取する皮膚生検により病理組織検査を行なうこともあります。
アレルギー検査
花粉症が疑われる場合には、特定の花粉の抗体の有無を調べる血液検査(IgE検査)や、皮膚にアレルゲンを少量注射し反応を見る皮内テストなどを行ないます。
細菌培養検査
皮膚炎や鼻炎が続く場合、細菌感染の可能性が疑われます。
そこで行なうのが、細菌培養検査です。
- 皮膚の赤みがひどい
- 膿が出ている
- 花見が黄色や緑色の場合
このような場合は、細菌感性が疑われます。
培養検査で、感染源となる細菌を特定することにより、適切な抗生物質を処方することができるのです。
レントゲン検査
慢性的な鼻水、くしゃみが見られる場合、鼻腔や気道の確認が必要です。
レントゲン検査により、肺や気管支の異常、鼻腔内の炎症や腫瘍の有無を確認します。
気管支内視鏡・CT検査
鼻腔内や気道内部をより精密に調べるために行なうのが、内視鏡やCT検査です。
内視鏡検査では、内視鏡で鼻の裏側や気道内部を確認していきます。
CT検査では、鼻腔や気管、肺などの断面像を撮影することにより、レントゲンより詳細まで確認することができます。
ただし、検査機械が高額であるため、大学病院や専門病院で行なうようになります。
花粉症の治療について
免疫の過剰な反応や炎症を抑えたり、皮膚のバリア機能を強化する治療がメインです。
アレルギー疾患は完治が難しいとされています。
しかしながら、適切な治療で症状を落ち着かせすことによって、普段通りの生活を送ることができます。
内服薬や注射の治療
炎症と痒みを抑える薬を使用します。
ステロイドや痒みが伝わるシグナルをおさえるアポキルを使用したり、抗ヒスタミン薬や免疫抑制剤を併用したりします。
外用薬
皮膚の一部のみ炎症がある場合は、ステロイド入りの軟膏や抗菌薬配合外用薬を用います。
痒みが強いときには、ローションやクリームを併用するのも良いでしょう。
食事療法
栄養バランスの整った食事、アレルゲンを含まないフードを選ぶことが大切です。
自宅でできる花粉対策とは?
花粉症の対策をお家で行なうこともできます。
ポイントは6つです。
- 散歩の際、服を着用し花粉がつかないようにする
- 散歩から帰ったら体を拭き、ブラッシングをする
- シャンプーは肌に優しい成分で保湿力が高いものを使用する
- シャンプーは2週間に1回を目安に
- 室内の清掃や空気清浄機を用いて清潔に
- 飼い主さんも外から帰ったら衣服は玄関で脱ぐ
まとめ
春や秋と言えば、過ごしやすい季節ですが、花粉症が出やすい季節でもあります。
- 花粉を家庭内に持ち込まない
- バランスの取れた食事
- 適切な治療の実施
- 生活環境の工夫
これらが必要です。
これらを実践して、愛犬と楽しい花粉症シーズンをお過ごしください。
この記事の監修者
獣医師 宮尾 岳
西新宿ペットメディカルクリニック 院長
新宿区の西新宿ペットメディカルです。
動物が病気になったときに治療することだけが獣医療ではありません。
日々の予防を喚起するのも自分の務めです。
日常の些細な疑問やケアからでも病院へ相談、もしくは足を運んで頂ければ幸いです。