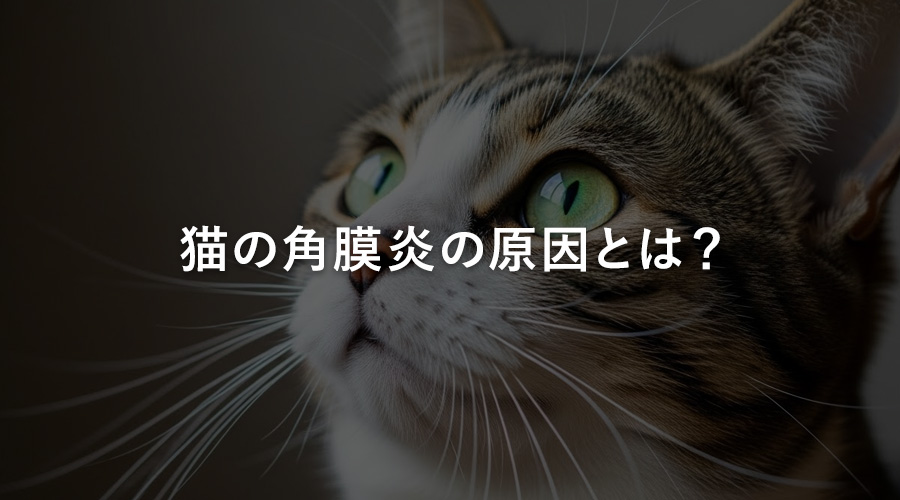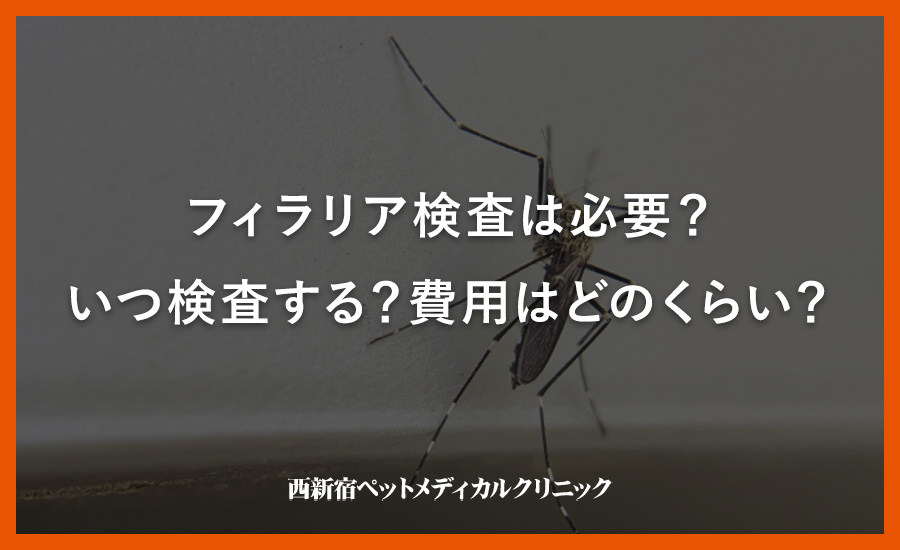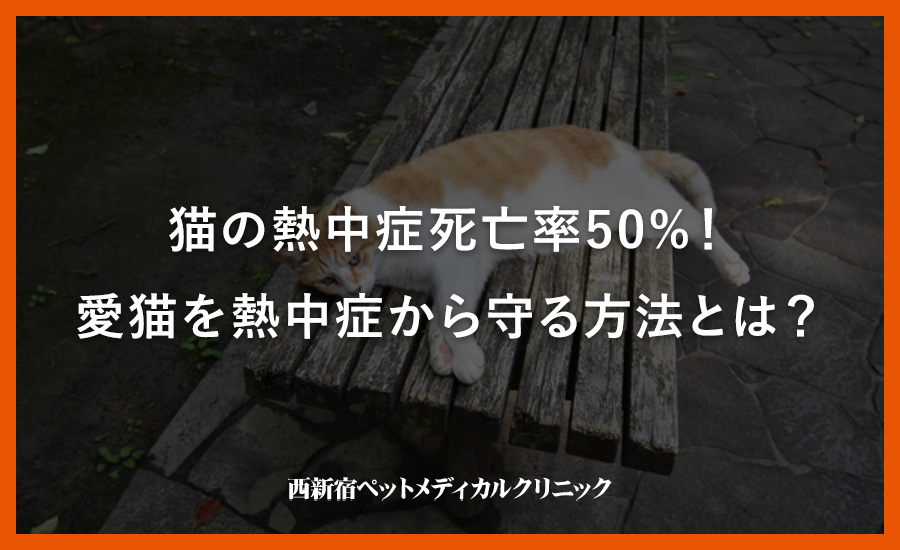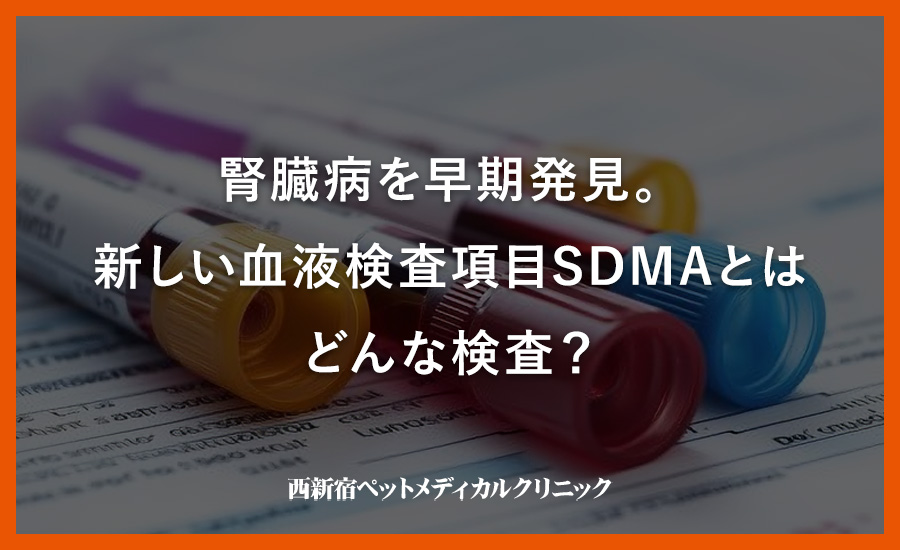あなたの愛猫の眼をじっと見てみてください。
キラキラしていますか?
このような様子が見られたら、角膜炎を発症しているかもしれません。
ここでは、このような症状をともなう猫の角膜炎について解説いたします。
猫の角膜炎とは?
猫の角膜とは、外から見える眼の表面部分を覆っている透明な膜の部分のことを指します。
よくカメラのレンズに例えられますが、カメラで言うと、もっとも手前のガラス面の部分に当たります。
猫の角膜の厚さはおよそ0.5mm程度で、角膜上皮、角膜実質、デスメ膜、角膜内皮と呼ばれる4層で構成されています。
透明で細胞が非常に規則正しく配置されているのが特徴です。
そんな角膜の役割は、眼球内部の網膜に光の強弱や色彩などの情報を正しく伝えるための透明さを保ちながら、眼球そのものを外部の刺激からまもる役割を担っています。
この角膜がさまざまな要因によって傷つき、炎症を起こしてしまった状態のことを角膜炎と言います。
猫の角膜炎の原因とは?
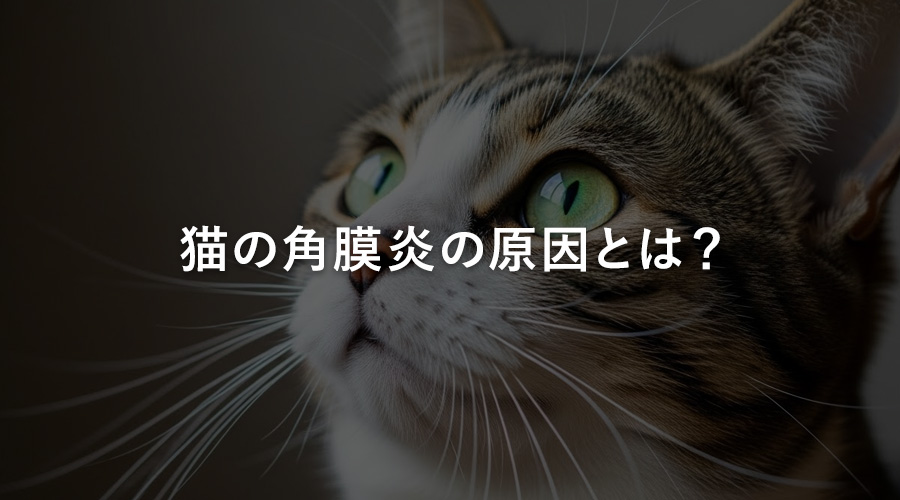
猫の角膜炎の原因はおもに、外部からの刺激によるものと、猫自身によるものに分けられます。
ここからは、猫の角膜炎のおもな原因について詳しく解説いたします。
外傷によるもの
猫の角膜炎の原因の多くが外傷によるものです。
ほかの猫とケンカをしたりじゃれているうちに、眼を傷つけてしまうことがあります。
ほかの猫とケンカをしている際、爪が眼球に刺さり、角膜に大きなダメージを与えるケースです。
深刻な場合は、爪が角膜を貫通し「角膜穿孔(かくまくせんこう)」と呼ばれる状態になることがあります。
このほかにも、ごみや異物が眼に混入し角膜を傷つけるケース、眼を気にして猫自身がこすってしまうことによって角膜を傷つけるケースもあります。
また化学的な刺激によって角膜炎を発症することもあります。
シャンプーをしたあと、すすぎが不十分で角膜炎を起こすケースもあります。
刺激性のある気体や液体が眼に入らないよう注意が必要です。
アレルギーによるもの
ノミなど外部寄生虫によるもの、エサの原料によるものの影響で猫がアトピー性皮膚炎を発症することがあります。
アトピー性皮膚炎を発症すると、皮膚に病変が表れ、かゆみを生じます。
かゆみを生じる箇所が眼に近い場合、かゆい箇所を掻いた際、眼や眼の周辺組織にダメージを与えることがあります。
ダメージを受けた箇所が角膜であれば、角膜炎を発症することになります。
感染症によるもの
感染症により角膜炎を生じることも決して少なくはありません。
感染症には、ウイルスや細菌、真菌によるものなどいろいろありますが、そのなかでも猫伝染性鼻気管炎いわゆる猫カゼと呼ばれるものは眼に病変を生じます。
これにより、結膜炎を発症し細菌感染も加わることにより、多量の目やにが見られるようになります。
結膜が腫れて感染したまま長時間が経つと、眼球に結膜が癒着するケースがあります。
これにより、眼球やその周辺組織が本来の機能を発揮することができなくなるとともに、症状の悪化を加速することにつながり、角膜炎を発症するという場合もあります。
この原因となる病原体には、猫ヘルペスウイルス、猫狩シウイルス、猫クラミジアなどがあります。
またクリプトコッカスという真菌が原因となる場合もあります。
クリプトコッカスは、角膜炎以外にも呼吸器、特に鼻腔に病巣をつくる病原体でもあります。
その他の原因
角膜炎は、ほかの眼の疾患の合併症として発症することもあります。
猫カゼと言われる猫伝染性鼻気管炎のように結膜炎から派生するもの、緑内障やブドウ膜炎といった眼球内部の問題が角膜に影響することもあります。
また、角膜に強い炎症が引き起こされる好酸球性角膜炎もあります。
これは、ヘルペスウイルスを保有している猫が多く発症するもので、免疫異常が関係していると言われていますが、はっきりとした原因はまだ解明されていません。
このほか、自発性慢性角膜上皮欠損症(SCCEDs)という角膜上皮の障害により、難治性の角膜炎や角膜潰瘍が起こる事例もあります。
猫の角膜炎の症状とは?
猫の角膜炎の症状については次のような症状があります。
- 強い痛み
- 眼を開けにくそうにする
- 涙の量が増加
- 涙の量が少ないドライアイ状態
- 眼の充血
- 目やにの増加
- 黒目が白く濁る
- 眼をよくこすっている
上記のような症状が見られた場合には、角膜炎の可能性があります。
早めに動物病院を受診するようにしましょう。
猫の角膜炎の治療法とは?
猫の角膜炎の治療法としては、おもに3つです。
- 損傷を受けた角膜の修復
- 炎症を抑える
- 感染のコントロールを行う
角膜のダメージが軽度であれば、抗炎症剤、抗生物質など点眼薬治療がおもになります。
猫カゼなどほかの疾患からくるものであれば、原因となっている病気の治療も同時に行うことになります。
角膜潰瘍や角膜専攻を起こしているような深刻な場合には外科的治療が必要となります。
このほか、角膜保護を目的とした動物用のコンタクトレンズを一定期間装着するという治療法もあります。
猫の角膜炎の予防法とは?
もっとも効果的なのは、角膜に刺激を与えそうなものを除去することです。
屋外であれば、猫の眼を傷つけそうな草木を除去したり、屋外に出てほかの猫との接触を防ぐために屋内飼育にするなども有効的です。
また猫カゼからの角膜炎誘発を防ぐためにワクチン接種をするなど予防に努めることも大切です。
まとめ
猫の角膜炎は、眼を開けづらいといった猫の症状から気づくことができます。
角膜炎は早めに治療をすれば、元通りの状態に戻すことが可能な病気です。
日頃から、愛猫の様子に気を配り、眼を気にしてよくこすっている、眼をあまり開けようとしないなどといった様子が見られたら、速やかに動物病院を受診するようにしましょう。
この記事の監修者
獣医師 宮尾 岳
西新宿ペットメディカルクリニック 院長
新宿区の西新宿ペットメディカルです。
動物が病気になったときに治療することだけが獣医療ではありません。
日々の予防を喚起するのも自分の務めです。
日常の些細な疑問やケアからでも病院へ相談、もしくは足を運んで頂ければ幸いです。